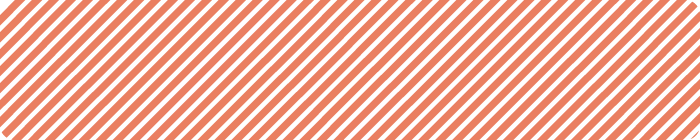よくあるキッチン後悔と対策|注文住宅で失敗しないためのコツ
.png&w=3840&q=75)
注文住宅のキッチンづくりで「理想」と「現実」のギャップに後悔する人は少なくありません。作業スペースの広さや高さ、色・デザイン、収納、設備など決めることが多く、毎日の暮らしに直結するため失敗しやすい空間です。本記事では、よくあるキッチンの後悔ポイントを整理し、暮らしに合った選び方の基準をまとめました。読み終えるころには、自分に合うキッチン像が明確になるはずです。
この記事を読むメリット
- よくあるキッチンの後悔事例と原因がわかる
- 大きさ・高さ・色・収納・設備ごとの注意点が整理できる
- 後悔しないためのチェックリストで選び方の基準が持てる
1. まず最初に:後悔しないためのチェックリスト

□ 大きさ・高さ|横幅・奥行き・通路・天板高さは家族の体格と使い方に合うか
□ 色・デザイン|汚れの見え方/素材の手入れ/照明下の見え方を確認したか
□ 形・レイアウト|I型・L型・Ⅱ型・対面(ペニンシュラ/アイランド)の長所短所は把握したか
□ 収納|吊り戸棚の有無・パントリー・小物/ゴミ箱まで配置を決めたか
□ 設備|食洗機サイズ、コンセント数と位置、冷蔵庫位置、手元灯は十分か
2. 注文住宅のキッチンで後悔が多いポイントとは
大きさ・高さに関する後悔
%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpeg?w=1200&h=799)
作業台の奥行きが浅い
カウンターの奥行きが不足すると、大きなまな板や調理器具を置いた際に窮屈さを感じます。
奥行きの目安 | 特徴 |
|---|---|
約60cm | 標準的な奥行き、一般的に多い |
約65cm | ゆとりを持たせた仕様 |
70cm以上 | アイランド型・特注仕様など、広さ重視 |
→ 奥行きは、どの調理器具を使うか・通路との兼ね合いを考えて決めるのが重要です。
通路幅が足りず家族とすれ違いにくい
キッチンの背面や横の通路は、作業効率に大きく影響します。
利用形態 | 推奨通路幅 |
|---|---|
一人で作業 | 約80〜90cm |
夫婦で使用 | 約100〜120cm |
複数人/広め | 120cm以上 |
補足:これらの数値は、オカムラホーム、リショップナビ、トーヨーキッチンスタイルなど複数の住宅会社で推奨されている一般的な目安です。
キッチン高さが合わず腰や肩がつらい
高さが体に合っていないと、毎日の調理で腰痛や肩こりにつながります。
多くのメーカーは 85・90・95cm の規格を用意していますが、平均的な90cmが必ずしも快適とは限りません。
よく使われる目安式
- 身長 ÷ 2 + 5cm
- 肘高 − 10cm
例:身長160cm → 約85cmが目安。
→ 家族で身長差がある場合は中間値を選ぶか補助台で調整し、最終的にはショールームで立って確認することが大切です。
色・デザインに関する後悔
%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpeg?w=1200&h=799)
色選び
色系統 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
黒・濃色 | 高級感・重厚感 | 空間が引き締まる | 指紋・水垢・油膜が目立つ |
白・淡色 | 明るく清潔感 | 空間が広く見える | 黄ばみ・色移りが目立つ |
グレー・ベージュ | 中間色 | 汚れが目立ちにくい | 無難・地味に感じる場合も |
仕上げ(扉面材など)
仕上げ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
鏡面 | 光沢あり | 明るい印象、高級感 | 指紋・拭き跡が残りやすい |
マット | 反射なし | 落ち着いた印象、擦り跡が目立ちにくい | 油汚れはやや残りやすい |
木目・石目調 | 凹凸あり | 汚れをカモフラージュ | 溝掃除がやや手間 |
天板素材
素材 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
ステンレス | 業務用で多い | 耐熱・衛生的・価格安め | 水垢・傷が目立つ |
人工大理石 | 樹脂系 | 色柄豊富、静音性あり | 熱に弱い、色移り注意 |
セラミック | 高硬度 | 傷・熱に強い、高級感 | 高価格・重量あり |
照明による見え方
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
昼白色(約5000K) | 白っぽい光 | 素材本来の色が出やすい | 冷たい印象になりがち |
電球色(約2700K) | 黄みのある光 | 温かみのある雰囲気 | 白系素材が黄ばんで見える |
演色性(Ra値) | 色の再現性 | Ra80以上なら自然な色味 | 低いと家具や食材の色が不自然 |
全体バランス
キッチン単体で見ると良くても、LDK全体で見たときに色が多すぎると雑多に感じることがあります。
- 色数:使う色は「床・壁・キッチン本体」の3色程度に絞るとまとまりやすい
- 明度差:扉・天板・床の明るさを揃えるか、差をつけてメリハリを出すかを意識する
- 家電色:冷蔵庫やレンジなどの色も考慮し、揃えると統一感が出る
👉 例:床がナチュラル木目、壁が白なら、キッチンはグレーや濃茶でバランスを取ると落ち着いた空間になります。
形・レイアウトに関する後悔
%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpeg?w=1200&h=790)
要約表
形 | 向くケース | 気をつける点 |
|---|---|---|
I型(壁付け) | 省スペ・コスト重視 | リビングに背を向けがち |
I型ペニンシュラ | 対面・会話重視、ほどよい省スペ | 壁側の暗さ/デッドスペース |
I型アイランド | 開放感・会話・見せる | 広さ・油ハネ・におい |
L型 | 作業効率・面積確保 | コーナーの死にやすさ |
U型 | 収納量・効率最優先 | 面積・圧迫感/動線固定 |
Ⅱ型(2列) | 分担・回遊性 | 通路干渉(開閉・人) |
I型キッチン(壁付け)
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
壁付けで一直線 | 省スペース・コスト抑えやすい | 作業中はリビングに背を向ける |
コンパクトで費用も抑えやすいですが、家族と会話しながら調理したい人には物足りなく感じることがあります。
I型ペニンシュラキッチン
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
一列型+片側が壁につく半島型 | 対面の開放感/アイランドより省スペース | 壁側が暗くなる・デッドスペース化しやすい |
リビングとつながる一体感があり人気のタイプ。ただし片側が壁になる分、照明や収納の工夫を怠ると後悔につながります。
I型アイランドキッチン
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
一列型+壁に接しない独立型 | 開放感抜群/家族やゲストと会話しやすい | 広い間取りが必要/油ハネやにおいが広がりやすい |
見た目は魅力的ですが、スペースを取るため「リビングが狭く感じる」という声も多いです。換気や動線計画とセットで検討することが重要です。
L型キッチン
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
2方向に直角配置 | 動線が短い/作業スペースが広い | コーナーがデッドスペース化/冷蔵庫位置に工夫必要 |
効率的に調理できますが、コーナー部分を活かせないと収納の無駄が生じます。回転ラックや引き出しを使うと改善できます。
U型キッチン
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
三方に囲まれるコの字型 | 作業効率が高い/収納量が多い | 広さが必要/動線が固定化されやすい |
複数人で料理する家庭や、調理器具を多く持つ人に向きます。ただしLDKが狭いと圧迫感が出やすいため要注意です。
Ⅱ型(2列型)キッチン
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
並行する2列に配置 | 調理と配膳の分業がしやすい | 通路が狭いと作業しづらい |
動線効率が高く、家事分担がしやすいのが強み。通路の広さを確保できるかが快適性の分かれ目です。
動線計画の後悔
どの形でも共通するのは「シンク・コンロ・冷蔵庫」の配置。ワークトライアングルと呼ばれる三角形の動線が大きく外れると、調理のたびに移動距離が増え、効率が落ちます。形だけでなく、動線と収納の計画を同時に考えることが重要です。
※補足|ワークトライアングルとは?
キッチンの使いやすさを決める重要な考え方に「ワークトライアングル」があります。これは シンク・コンロ・冷蔵庫の3点を結んだ動線 のことを指します。3辺の合計距離が 360〜600cm 程度に収まると、調理や配膳がスムーズになりやすいとされています。距離が長すぎると移動が増えて疲れやすく、短すぎると窮屈になるため、バランスが大切です。
効率的に配置されたキッチンは、調理のスピードが上がるだけでなく、配膳や片付けもスムーズに進みます。さらに、ゴミ箱や収納棚など周辺設備の位置も決めやすくなるため、全体的な使いやすさが向上します。
収納に関する後悔
%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpeg?w=1200&h=799)
要約表
テーマ | あるある後悔 | 事前対策 |
|---|---|---|
吊り戸棚 | 高すぎて使わない/圧迫感 | 到達高さ確認・可動棚・踏み台運用 |
吊り戸棚なし | 収納不足 | 代替:パントリー/カウンター下 |
パントリー | 狭くて機能しない | 置く物と回遊先(冷蔵庫・勝手口)で設計 |
引き出し | 深さ不一致で入らない | 鍋・フライパンの“現物寸法”で割付 |
オープン収納 | ほこり・生活感 | 維持できる運用か事前に試算 |
ゴミ箱 | 置き場がない | 分別数・容量を先に決める |
小物・調味料 | 散らかる | 仕切り/コンロ脇“ちょい置き” |
吊り戸棚
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
上部に取り付ける収納 | 大容量を確保できる/調理器具の定位置になる | 高すぎて使わない/圧迫感が出る |
「収納不足防止」として設けても、手が届かず実際は使わなくなるケースが多いです。
吊り戸棚なし
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
吊り戸棚を設けない | 開放感がある/リビングとつながりやすい | 収納不足になりやすい |
見た目はすっきりしますが、代わりにパントリーやカウンター下収納を用意しておかないと後悔しやすいです。
パントリー
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
食品や備蓄をまとめて収納 | 在庫管理がしやすい/まとめ買いに便利 | 狭すぎると活用できない/動線を圧迫する |
冷蔵庫や勝手口の位置とセットで考えないと「取りに行きにくい収納」になります。
引き出し収納
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
下部を引き出しにする | 奥まで見やすい/出し入れが楽 | 深さが合わないと鍋やフライパンが収まらない |
浅すぎる・深すぎると不便。入れる物を想定して設計するのが必須です。
オープン収納(見せる収納)
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
扉を付けない収納 | 出し入れが簡単/おしゃれに見せられる | ほこりがたまりやすい/生活感が出やすい |
雑誌やSNSでは人気ですが、日常的に維持できるかを考える必要があります。
ゴミ箱置き場
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
専用スペースを設ける | 動線に組み込みやすい | 忘れると通路や壁際に置くことになり邪魔 |
後から「置き場がない」と気づく典型的な後悔。分別数や大きさを先に決めておくと安心です。
小物・調味料収納
特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
仕切りや専用ラックを設ける | 調味料や小物が整頓できる | 計画しないと乱雑になりやすい |
コンロ脇や引き出しにちょい置きスペースを作ると調理効率が上がります。
👉 収納は「量」だけでなく 使う場所・高さ・動線 を意識することが後悔防止につながります。
3. なぜキッチンで「後悔」が起こりやすいのか

キッチンは毎日使う場所で、自由に決められる分だけ失敗もしやすい空間です。
- 使用頻度が高く、小さな不便が積み重なる
- 形・高さ・色・収納など決めることが多い
- 家事効率や生活動線に直結する
SNSやモデルハウスと実際の暮らしのギャップ
キッチン選びではSNSやモデルハウスを参考にする人が多いですが、ここに落とし穴があります。
- SNSの写真:生活感を省いた映え重視。維持が大変なケースも
- モデルハウス:広い間取りや高グレード仕様が前提で、実際の土地や予算では再現しにくい
→ 理想をそのまま取り入れると「憧れたのに使いにくい」と後悔につながります。
生活スタイルや家族構成を想定できていないことが原因
暮らしに合った検討不足も後悔の原因です。
- 家族構成:子育て世帯なら目が届くか、高齢者と同居なら高さや動線は負担にならないか
- 家事分担:一人で使うか、複数人で同時に立つかで通路幅が変わる
- 将来の変化:今は便利でも、数年後の暮らしで不便になることも
後悔の原因まとめ
キッチン後悔は「選択肢の多さ」と「理想と現実のギャップ」が原因です。
SNSの印象に流されず、家族の生活スタイルに合わせて選ぶことが何より大切です。
4. まとめ
%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpeg?w=1200&h=719)
後悔しないキッチンは、数字(寸法)×暮らし(使い方)のすり合わせで決まります。ぜひ今回のチェックリストを利用し、設計段階での“抜け漏れ”を一緒に潰していってください。
1つの選択肢「まどりLABO」
まどりLABOでは、AIを使って自分の条件に合わせた間取りを簡単に作成できます。気に入った間取りが見つかったら、そのまま複数の住宅会社へ無料で見積もりを依頼することも可能です。
SNSや雑誌で見た理想を、自分の土地・予算・暮らしに合わせて具体化する手軽な手段です。ぜひまどりらぼを通して複数見積もりをし、「理想と現実のギャップ」で後悔するリスクをぐっと減らして行きましょう。
まどりLABOでは、AIを使って条件に合わせた間取りを手軽に作成できます。気に入ったプランがあれば、そのまま複数の住宅会社へ無料で見積もりを依頼することも可能です。
SNSや雑誌で見た理想を“自分たちの家づくり”に落とし込み、現実的なプランとして比較検討する大きなきっかけとなることでしょう。複数の見積もりを取ることで選択肢が広がり、納得のいく家づくりにつながります。
👉 ぜひまどりLABOを活用し、「理想と現実のギャップ」による後悔を減らしていきましょう!

まどりLABO編集部|代表 野口雄人

東大卒の設計士・一級建築士・エンジニアなどで構成。間取りが大好きなオタクたちの集団で、間取りが好きなあまり間取りをAIで自動生成できるサイトを作成しました。代表の野口は東京大学・東京大学大学院で建築学を専攻しました。