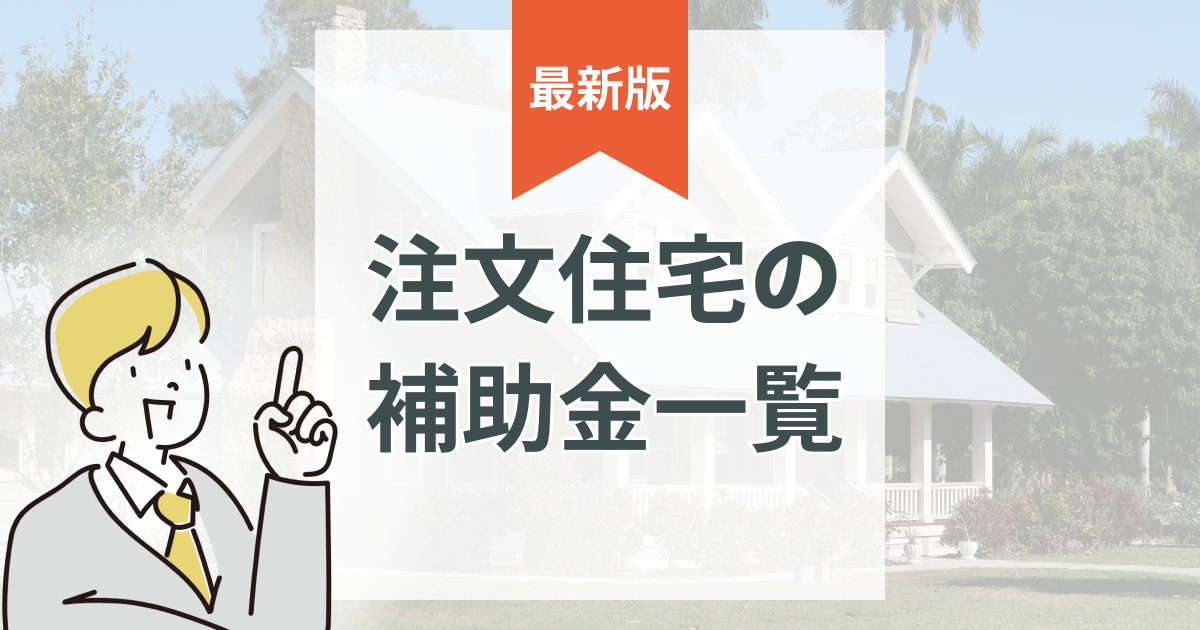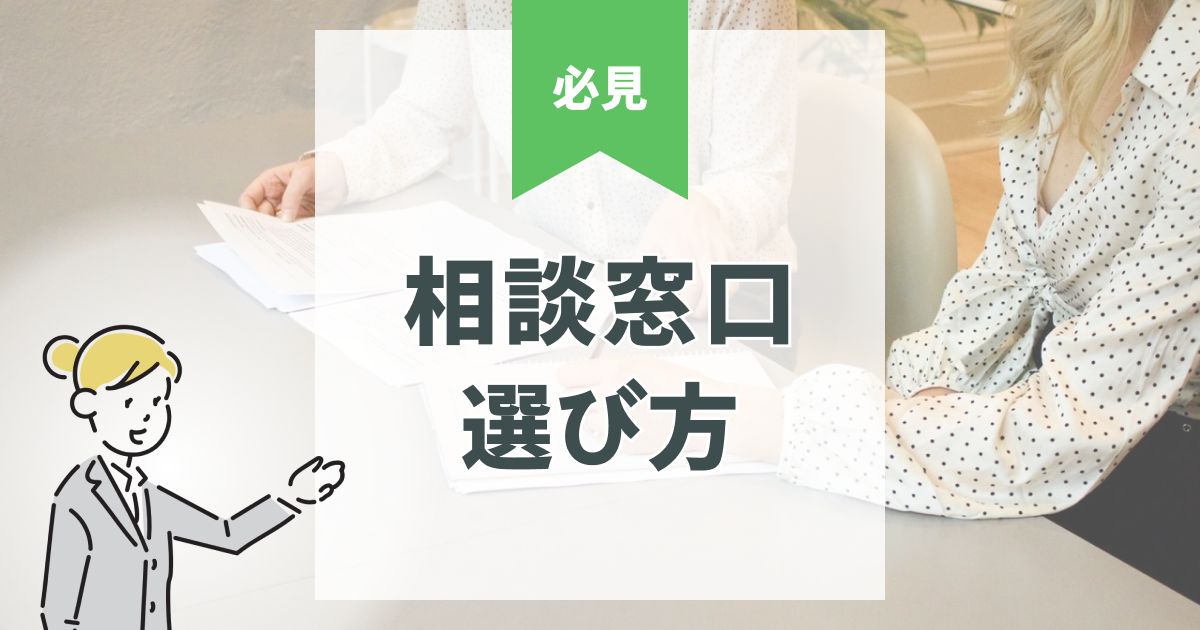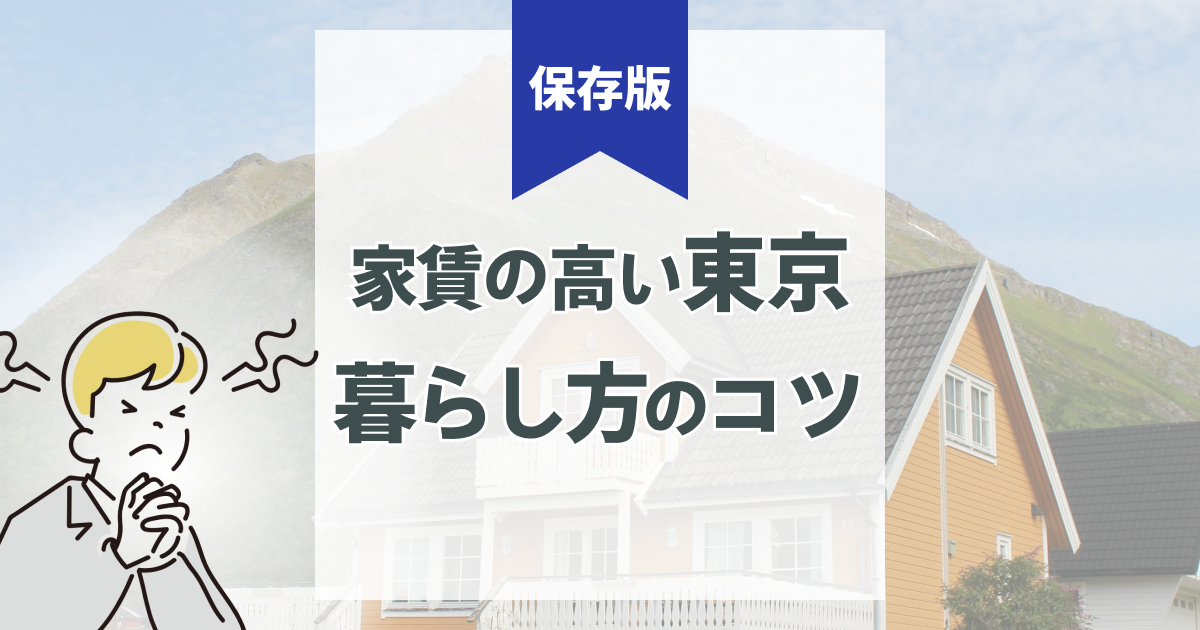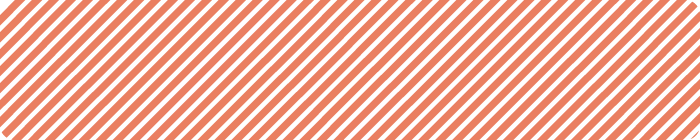【FP監修】2025年版ZEH住宅ローン控除のメリットを徹底解説
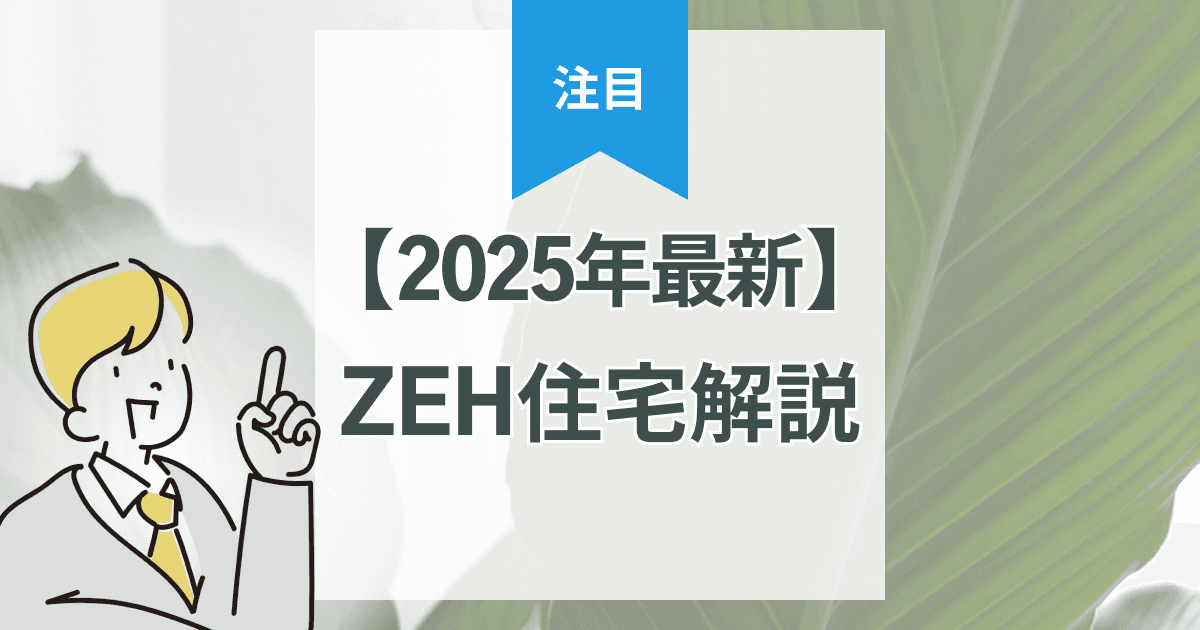
【FP監修】 2025年版 住宅ローン控除・補助金の最新制度に対応しています
「ZEHは高いし…」と決めつける前に、少しだけ立ち止まってください…!2025年の住宅ローン控除では、ZEH水準かどうかで借入限度額に大きな差が出ます。
知らないまま建てると、数百万円分の控除枠を逃すことも。
家を建てる前に、最新の減税ルールと“いくら得するのか”を必ず押さえておきましょう!
この記事を読むメリット
- 2025年版|ZEH水準での住宅ローン控除額と借入限度額が分かる
- 太陽光なしの「ZEH Oriented」は満額控除の対象になるかが分かる
- Nearly ZEH/ZEH Readyなど区分ごとの扱いが分かる
- 補助金と住宅ローン控除を併用する際の計算ルールと注意点を学べる
- 初期費用を“控除+補助金+光熱費削減”で回収する判断基準を学べる
1. ZEH水準で住宅ローン控除はどう変わる?【2025年の控除額と限度額】

2025年の家づくりにおいて、ZEH水準を選ぶ最大の金銭的メリットは「住宅ローン控除の借入限度額が大幅に増えること」です。
「省エネ基準適合(義務化ライン)」ギリギリの性能で建てるのと、ワンランク上の「ZEH水準」にするのとでは、控除対象となる借入額の上限に500万〜1,500万円もの差がつきます。
まずは、この「金額の差」をシミュレーションしてみましょう。
借入限度額とは、住宅ローン控除の計算に使ってよいローン残高の“上限”のこと。(銀行で借りられる額(年収で決まる“融資限度額”)とはまったく別物。)実際にいくら借りていても、この上限までしか控除額の計算に反映されない。一方、控除額とは、その年に税金から差し引かれる金額で、年末時点のローン残高(ただし限度額まで)に0.7%を掛けて求める。借入限度額が大きいほど、計算に使える残高も増えるため、年間の控除額、さらに13年間の総額が大きくなる。「ZEHが有利」という話は、この“控除枠の広さ”が理由である。
一般住宅とZEH水準の控除額比較(2025年)
2025年(令和7年)入居の場合、年末ローン残高の0.7%が所得税等から13年間控除されます。その上限となる「借入限度額」は以下の通りです。
住宅の区分 | 借入限度額 | 年最大控除額 | 13年間の最大控除額 |
ZEH水準 (子育て・若者夫婦) | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 |
ZEH水準 (一般世帯) | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 |
省エネ基準適合 (ZEH未満) | 3,000万円 | 21.0万円 | 273.0万円 |
※子育て世帯:19歳未満の子がいる、若者夫婦世帯:夫婦いずれかが40歳未満
最大136万円の差!「ZEH水準」にするだけで枠が広がる
表の通り、子育て世帯がZEH水準の家を建てた場合、省エネ基準適合住宅と比べて最大136.5万円(409.5万 - 273万)も控除総額が増える可能性があります。
「ZEHは建築費が高い」と思われがちですが、この減税メリットに加え、光熱費削減効果や補助金(後述)を合わせれば、初期費用の差額を回収できるケースは少なくありません。逆に言えば、「ZEH水準にしないことで、数百万円分の控除枠を捨ててしまう」とも言えるのです。
なぜZEH水準が優遇されるのか?
2025年4月から、すべての新築住宅に「省エネ基準への適合」が義務化されています。つまり、省エネ基準適合住宅はあくまで「最低ライン」となります。 政府はより高い性能を持つZEH水準の普及を推進しているため、「義務化ライン(省エネ適合)」と「推奨ライン(ZEH水準)」の間には、税制優遇にはっきりと差がつけられているのが現状です。
では、「ZEH水準」と認められるためには、必ず太陽光パネルが必要なのでしょうか? 実は、パネルなしでも満額控除を受けられるケースがあります。次の章で詳しく解説します。
2. ZEH Oriented・Ready・Nearlyで住宅ローン控除の対象は変わる?

ZEHについて調べていると、「ZEH Oriented」や「ZEH Ready」といった言葉が出てきて混乱することはありませんか?
「完全なZEHじゃないと、住宅ローン控除の金額が減ってしまうのでは……」と不安になる方も多いのですが、結論から言うとすべて同じ扱いです。安心してください。
住宅ローン控除の判定において、これらはすべて「ZEH水準省エネ住宅」というひとつの大きな枠組みに分類されます。
つまり、太陽光パネルを載せない「ZEH Oriented」であっても、満額(子育て世帯なら借入限度額4,500万円)の控除対象になるのです。
区分の違いはあくまで “性能の段階差” であり、控除の仕組みとは切り離されています。
【一覧表】ZEHの種類と住宅ローン控除の扱い
それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。「控除の扱い」がすべて同じである点に注目してください。
種類 | 太陽光パネル | エネルギー削減率 | 住宅ローン控除の扱い |
|---|---|---|---|
ZEH | 必須 | 100%以上 | ZEH水準 (満額) |
Nearly ZEH | 必須 | 75%以上 | ZEH水準 (満額) |
ZEH Ready | 推奨 (なくても可) | 50%以上 | ZEH水準 (満額) |
ZEH Oriented | 不要 | 20%以上 | ZEH水準 (満額) |
違いは「太陽光パネル」の有無だけ
これらの4つは創エネ(太陽光)をどうするかで区分が変わります。
- ZEH / Nearly ZEH:パネル必須。エネルギー実質ゼロを目指す。
- ZEH Oriented:パネル不要。都心や日陰の立地でもOK。
「屋根が小さくてパネルが載らない」場合でも、断熱性能さえ満たせば最大の控除枠が使えます。
無理に太陽光を載せなくても恩恵を受けられるのが、今の制度の大きなメリットです。
控除額は同じ。ではどれを選べばいい?
税制優遇に差がない以上、選ぶ基準は「土地の条件」と「欲しいメリット」の2つになります。
ZEH Oriented(初期費用・デザイン重視):
太陽光が必須ではないため、都心の狭小地や日当たりの悪い土地でも採用しやすいのが特徴です。屋根形状の制約が少ないため、間取りやデザインの自由度を優先したい方に向いています。
ZEH / Nearly ZEH(光熱費削減・防災重視):
太陽光発電でエネルギーを作るため、月々の電気代を大幅に減らしたい方に最適です。初期費用はかかりますが、日々のランニングコスト削減と、停電時の安心感が手に入ります。
ZEH Ready(性能バランス重視):
Orientedより高い断熱・省エネ性能を持ちつつ、フルZEHほどの発電量は求めないタイプです。「性能はしっかり上げたいが、パネル容量は屋根に合わせて調整したい」というバランス派に適しています。
性能を高めすぎる必要はありませんが、ご自身の土地や暮らしに合う水準を選ぶことで、光熱費の負担を減らし、快適さを保ちやすくなります。控除の仕組みが変わらないからこそ、無理のないプランで比較検討してみましょう。
3. 住宅ローン控除と補助金は併用できる? 資金計画の注意点

ZEH水準の家を建てるなら、住宅ローン控除だけでなく「補助金」もフル活用したいですよね。 結論から言うと、国の補助金や自治体の助成金と、住宅ローン控除は原則として併用可能です。
特に2025年は、ZEH水準の住宅に対して以下のような大型補助金が用意されています。
- 子育てエコホーム支援事業:1住戸につき最大80万円(ZEH水準住宅)
- 戸建住宅ZEH化等支援事業:基本55万円〜(+蓄電池、+高性能などで加算あり)
これらを受け取りつつ、住宅ローン控除で所得税の還付を受ける「二重取り」ができるのが、ZEHの大きな魅力です。ただし、資金計画を立てる上で一つだけ注意しなければならない「計算のルール」があります。
補助金を受け取ると「控除対象額」が減る?
意外と知られていないのが、「補助金をもらった分は、住宅ローン控除の計算上の『家の価格』から差し引かなければならない」というルールです。
住宅ローン控除は、年末のローン残高に対して計算されますが、実は以下の2つのうち「低いほう」が対象額になります。
- 年末のローン残高
- 住宅の取得対価(家の購入価格) - 補助金の額
少しややこしいので、具体例で見てみましょう。
【例】4,000万円の家を建て、100万円の補助金をもらい、フルローン(4,000万円)を組んだ場合 |
|---|
この場合、税務署の計算では「家の取得価格」は4,000万円ではなく、補助金を引いた「3,900万円」とみなされます。 ローン残高が4,000万円あったとしても、控除の対象になるのは3,900万円までとなってしまいます。 |
それでも補助金はもらうべき!
「じゃあ、損をするの?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。 補助金は「現金で100万円が手に入る」という確実なメリットです。
控除対象額が多少減って税金の戻りが少し減ったとしても、トータルで見れば補助金をもらったほうが圧倒的にお得なケースがほとんどです。
ただ、「ローン残高のすべてが控除対象になるつもりで計算していたら、確定申告で数字が合わない!」と慌てないよう、「補助金分は控除対象から引かれる」ということだけ、頭の片隅に置いておいてくださいね。
4. 控除だけじゃない! 経済メリットから考えるZEH設計のコツ

ここまで住宅ローン控除や補助金のお話をしてきましたが、やはり気になるのは「で、結局トータルで損なの? 得なの?」という点ではないでしょうか。
ZEHにするための初期費用は、一般的な住宅に比べて200〜300万円ほど高くなる傾向があります。
この差額をどう回収し、メリットに変えていくかが設計の腕の見せ所です。
「初期費用」vs「回収できる金額」のバランス
ZEHは「高い」と言われますが、長期的な視点で見ると、そのコスト差は意外と埋まるものです。ざっくりとした損益分岐のイメージを持ってみましょう。
初期コスト増:約250万円
戻ってくるお金:
- 住宅ローン控除の増額:+数十万〜百万円超(※借入額による)
- 補助金:+55万〜100万円
- 光熱費削減:+100万円以上(月1万円削減×10年〜)
こうして並べてみると、10年〜15年ほどのスパンで見れば、初期費用の元を取りつつ、その後は「光熱費が安い家」という資産が残ることがわかります。
ZEHは「光熱費と税金の先払い」と考えると、決して高い買い物ではないのです。
「売電」より「自家消費」と「快適性」を重視する
これからのZEHで失敗しないコツは、電気を売って儲けることよりも「電気を買わない暮らし」を目指すことです。 売電価格が下がっている今、発電した電気は自宅で使い切る(自家消費)のが最も経済的です。
また、お金に換算しにくいですが、「快適性」も強烈なメリットです。 高断熱なZEHは、夏は涼しく冬は暖かい魔法瓶のような家です。エアコン効率が良くなるだけでなく、冬場のヒートショックのリスクも軽減されます。「医療費のかからない健康な体」も、ZEHがもたらす隠れた経済効果と言えるでしょう。
5. まとめ:ZEHは「控除・補助金・光熱費」の3点セットで判断しよう

項目 | ZEH水準 (Oriented / Ready含む) | 省エネ基準適合 (一般的な住宅) |
|---|---|---|
① 住宅ローン控除 (借入限度額) | 最大 4,500万円 ※控除額 約410万円 | 最大 3,000万円 ※控除額 約273万円 |
② 補助金 | 対象(55万〜100万円など) | 対象外が多い |
③ 光熱費 | 大幅ダウン (高断熱+省エネ機器) | 標準的 |
結論 | 初期費用はかかるがトータルで回収しやすい | 初期費用は安いが税制・光熱費で損をしやすい |
2025年のZEHは、単なるエコ住宅ではありません。
今回解説した「住宅ローン控除(最大4,500万円枠)」と「補助金」、そして「光熱費削減」。
この3つを組み合わせ、長い目で見て家計負担を減らすための「賢い投資」です。
目先の建築費だけでなく、10年・20年先の収支トータルで考えることが、後悔しない家づくりの鍵となります。
あなたの理想の家、いくらで建つか知っていますか?
複雑な計算をする前に、まずは「そもそもZEHの家はいくらするのか?」という相場感を知ることも、失敗しない家づくりの重要なステップです。
「まどりLABO」なら、スマホから希望条件を入力するだけで、AIが間取りプランを提案。
さらに「この間取りならいくら?」という見積もりを、複数の会社から無料で取り寄せることができます。
具体的な金額が見えてくれば、ローン計画や控除のメリットもより現実的に考えられるようになります。
まずは情報収集の一つとして、シミュレーション感覚で試してみてはいかがでしょうか。
[[article-card:https://madori-labo.com/articles/ideal-layout-simulation]]

まどりLABO編集部|代表 野口雄人

東大卒の設計士・一級建築士・エンジニアなどで構成。間取りが大好きなオタクたちの集団で、間取りが好きなあまり間取りをAIで自動生成できるサイトを作成しました。代表の野口は東京大学・東京大学大学院で建築学を専攻しました。