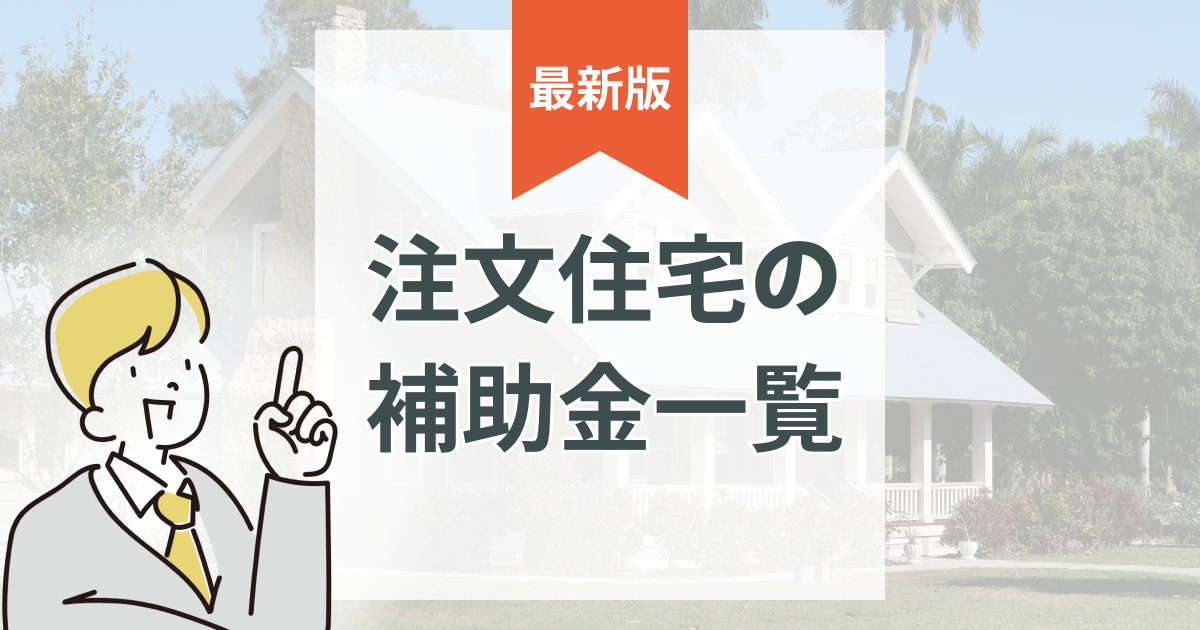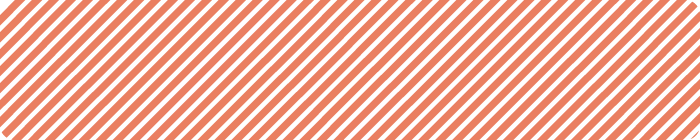家を建てる20代必見!費用・制度・流れ・成功の秘訣を徹底解説
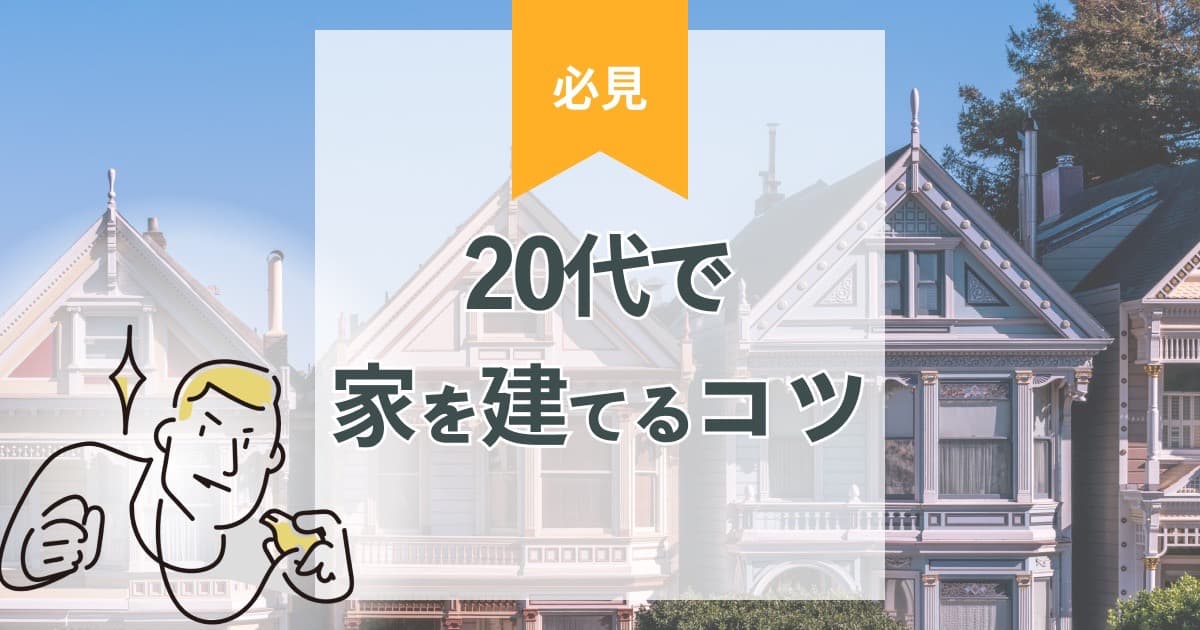
家を建てるのは30代以降――そう考える人が多い中で、「20代で建てても大丈夫?」と悩む声が増えています。収入の安定、転勤、家族計画など、若いうちの決断には不安もつきものです。
本記事では、20代で家を建てる際のメリット・デメリット、注意点と失敗しないポイント、そして転勤や家族変化への対応策・補助金制度をわかりやすく整理しました。
この記事を読むメリット
- 20代で建てるメリット・リスクの実像がわかる
- 転勤・家族構成の変化に備える方法が理解できる
- 補助金を活用して“無理のない家づくり”を実現できる
1. 20代で家を建てるメリット・デメリット

20代で建てる3つのメリット(ローン・将来設計・安定基盤)
20代で家を建てる最大のメリットは、「時間を味方につけられること」です。
主なメリット
- 住宅ローンを早く組めるため、返済期間を長く設定できる
- 昇給や転職などで収入が増えれば返済負担が軽くなる
- 若いうちに住まいの基盤を持ち、ライフプランを立てやすい
20代で家を建てれば返済開始が早い分、完済時の年齢も下げられます。
返済期間を長くできるため月々の負担を抑えやすく、将来の繰上げ返済にも柔軟に対応できます。
また「家を持つ」ことで結婚や子育てなどの将来設計が立てやすくなるのも大きな利点です。
20代だからこそ起こりやすいデメリット(収入・転勤・頭金)
一方で、20代はキャリアや生活が大きく変化する時期。
この「変化の多さ」が家づくりのリスクにもなり得ます。
主なデメリット
- 収入が安定しておらず、借入可能額が限られる
- 結婚・出産・転勤などライフイベントの変化に対応しづらい
- 頭金が少なく、借入額や返済総額が増えやすい
「想定外の環境変化」により家の立地や間取りが合わなくなるリスクがあります。
また、貯蓄不足から頭金を十分に用意できず、ローン総額が膨らむ点も注意すべきです。
「早いかどうか」よりも“自分に合うかどうか”で判断する
20代で家を建てるかどうかを決める際は、
「年齢が早いかどうか」ではなく、「自分のライフプランと合っているか」で判断することが大切です。
ローンを早く始めるメリットと、ライフイベントの不確実性をどう調整するか。
このバランスを見極めるのがポイントです。
目安としては、
- 頭金をどの程度用意できるか
- 今後30年のライフプランをどこまで描けるか
この2点を考えたうえで、無理のない返済計画を立てられるなら、20代で家を建てるのは十分に現実的です。
2. 20代で家を建てるときの注意点と失敗しないポイント

結婚・出産・転勤など、変化を見越した家づくりを
【ライフイベントと家づくりの失敗例】
ライフイベント | よくある後悔ポイント | 対策の考え方 |
|---|---|---|
結婚・出産 | 部屋数が足りない、収納が少ない | 将来仕切れる部屋・可変性のある間取りに |
転職・転勤 | 通勤に不便、勤務地が変わる | 駅近・交通アクセスを重視する |
リモートワーク | ワークスペースがない | 個室or半個室を想定して設計 |
👉 「今の暮らし」ではなく「5〜10年後の暮らし」を想像して間取りを考えるのがポイント。
10年先も安心できるローンと収入設計を
【ローン設計で意識したいポイント3つ】
- 「今払える」よりも「将来も払える」金額を基準にする
- 固定金利・長期返済で安定性を重視
- 余裕ができたら繰上げ返済で負担を軽減
💬 ポイント |
|---|
住宅ローンは「人生の長距離マラソン」。 無理なく走り続けるためには、ペース配分(返済計画)が何より大事です。 |
土地と間取りで“後悔ポイント”を防ぐ
【土地選び・間取りのチェックリスト】
土地選び
- 周辺の教育・医療・交通の利便性
- 再開発や人口動態など将来性
- 売却・賃貸時の資産価値
間取り
- 収納量は十分か
- 家事・生活動線がスムーズか
- 家族構成が変わっても対応できるか
👉 専門家や第三者に「実際に住んだときのイメージ」を確認してもらうのもおすすめです。
20代の家づくりは“変化に強い設計”がカギ。
現在よりも未来の暮らしを想像できる人が、後悔のない家を建てられます。
3. 転勤や家族構成の変化が不安な人へ

「売る」「貸す」という選択肢を知っておこう
- 売る:中古市場は継続的に動いており、首都圏中古マンションの「登録→成約」までの平均は近年80日前後。エリア差はあるものの、数カ月スパンの売却が目安です。(参考資料)
- 貸す:住宅ローン返済中でも、転勤などやむを得ない事情なら賃貸可のケースあり(フラット35の例)。ただし金融機関への届出・承諾は必須。無断賃貸は契約違反になり得ます。(フラット35)
- 契約形態:一定期間で確実に終了できる定期借家契約を選ぶと、戻る前提の“留守宅運用”がしやすい。
リセールしやすいエリア・家の条件とは
- 交通利便(駅・路線・バス本数)、生活利便(買物・医療・教育)
- ハザードマップの水災害リスク確認(関心は年々高まる傾向)(国土交通省)
- 汎用性の高い間取り(2LDK⇄3LDK可変など)/十分な収納・動線
- 管理・修繕の履歴(インスペクション活用で安心材料に)
“ずっと住む前提”じゃなくても大丈夫。家は資産になる
出口を最初に設計:
- 売却…近隣の成約相場と在庫・滞留日数をチェック。
- 賃貸…金融機関へ事前相談/定期借家で期間を区切る。(参考資料:フラット35)
- 住み替え…住み替えローンで旧居ローンが残っても対応できる場合あり。(参考資料:みずほ銀行)
ポイントは「売る or 貸すの見通しが立つ立地と間取り」を選ぶこと。これが、20代でも“動ける”家にする最大の保険です。
[[article-card:https://madori-labo.com/articles/home-downpayment-guide]]
4. 20代が利用できる減税制度・補助金・その他支援制度【2025年版】

20代が利用できる補助金・支援制度【2025年版】
地域独自の支援制度
移住促進や定住促進の目的で、自治体によって数十万円〜数百万円規模の補助が受けられるケースがあります。制度の条件や金額は、各自治体ごとに確認が必要です。
- 北海道赤井川村では、住宅を新築し10年以上住めば 最大300万円の建設資金支援、さらに 固定資産税が3年間半額になる制度があります 。
- 一部自治体では、20年間定住を条件に土地・住宅が無償譲渡される制度も確認されています。
このように条件や金額は大きく異なるため、「移住先の自治体名 住宅 補助金」「移住支援 金額」などのワードで検索するのが効果的です。
20代で家を建てる場合、今後の転職や子育てのライフプランに合わせて、地域の制度をうまく組み合わせることが重要です。
補助金・支援制度は年度ごとに内容が変わるため、最新情報をチェックすることが欠かせません。
まどりLABOでは、制度の詳細や申請のポイントをまとめた記事も公開しています。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、ローン残高の0.7%を所得税・住民税から控除できる制度です。
2025年も継続しており、新築の場合は13年間適用されます。
若いうちに家を建てれば、返済初期の負担を軽くでき、長期的に大きな節税効果が期待できます。
子育て世帯・若者向け補助金
20代は「子育て世帯」や「若者世帯」として優遇を受けやすい年代です。
代表例は「こどもエコすまい支援事業」。高性能住宅を建てる際に最大100万円の補助が受けられます。
また自治体ごとに、結婚・子育て支援と連動した住宅補助金が設けられているケースも多く、20代で建てるメリットの一つといえます。
地域ごとの支援制度を活用する方法
国の制度に加え、各自治体独自の支援も見逃せません。
例として、移住促進のために数十万円の補助を出す地方自治体や、固定資産税の減免を行う都市部もあります。
特に20代で家を建てる場合、今後の転職や子育てのライフプランに合わせて、地域の制度をうまく組み合わせることが重要です。
補助金・支援制度は年度ごとに内容が変わるため、最新情報をチェックすることが欠かせません。
まどりLABOでは、制度の詳細や申請のポイントをまとめた記事も公開しています。
5. まとめ|「早い」ではなく「自分に合っているか」で考えよう

20代で家を建てる価値の再整理
20代で家を建てることは、“早すぎる”というより“時間を味方につける”選択です。
ローンを早く組めば定年前に完済しやすく、家賃を資産に変えることもできます。
もちろん、転勤や収入変化への不安はありますが、売却や賃貸などの選択肢を知っておけば問題ありません。
大切なのは「一生住む家」ではなく、「今の自分に合う暮らし」を選ぶことです。
後悔しないために、まずやるべきこと
勢いで建てる前に、ライフプランと資金計画を一度整理しましょう。
- 無理のない返済額をシミュレーション
- 将来の変化も見越した柔軟な間取り
- 利用できる補助金をチェック
“早いかどうか”より、“自分にとってちょうどいいタイミングか”。
その視点が、後悔しない家づくりにつながります。

まどりLABO編集部|代表 野口雄人

東大卒の設計士・一級建築士・エンジニアなどで構成。間取りが大好きなオタクたちの集団で、間取りが好きなあまり間取りをAIで自動生成できるサイトを作成しました。代表の野口は東京大学・東京大学大学院で建築学を専攻しました。
.png)
.png)